最近ニュースや自治体の発表で耳にするようになった 「ミズワタクチビルケイソウ」。
名前を聞いただけでは何の生き物か分からない方も多いのではないでしょうか?
実はこの外来藻類が川に広がると、水中で綿のような群生をつくり、 魚や水生昆虫の生息に悪影響を与えるだけでなく、釣り人の仕掛けや道具にも大きな被害をもたらす ことが分かっています。
この記事では、
- ミズワタクチビルケイソウとはどんな生き物なのか
- 何が問題なのか(生態系への影響・釣り具トラブル)
- 釣り人ができる対策(消毒方法など)
をわかりやすく解説します。
ミズワタクチビルケイソウとはどんな生き物?

名前の由来と分類
ミズワタクチビルケイソウ(学名 Cymbella janischii)は、北米原産の外来性の珪藻(けいそう)の一種です。
「水綿(ミズワタ)」のように白くふわふわした群体を形成することから、この和名がつけられました。
珪藻とは、ガラス質の殻をもつ藻類の仲間で、その中でもミズワタクチビルケイソウは細胞の長さが0.2mmほどと大型。
細胞の端から粘質の柄を出し、石などに付着して群体を形成します。
どんな環境で繁殖するのか
この珪藻は冷たい流水環境を好み、細胞分裂を繰り返して群体を厚く成長させます。
時には厚さ数センチに及ぶ群体となり、川底の石を覆い尽くします。
日本での発見状況
近年は九州や関東の河川上流で大繁殖して問題になっていましたが、2022年5月に琵琶湖へ流入する安曇川で近畿地方初確認。
この観察記録は同年12月、日本珪藻学会誌「Diatom」に論文として発表されました。
ミズワタクチビルケイソウは何が問題?

生態系への深刻な影響
川底を厚い群体で覆い、付着藻類を食べる水生昆虫が減少。
その結果、アユなどの魚類が著しく減少した事例が各地で報告されています。
釣り具にまとわりつく被害
仕掛けやライン、タモ網、ウェーダーなどに群体が絡みつき、取り除くのが困難。
釣果や釣行の快適さを損なう大きな要因になります。
分布拡大のリスク
釣り具やウェーダーに付着したまま別の川で使用すると、分布域を拡大させるリスクがあります。
全国から釣り人が集まる琵琶湖周辺では、拡散リスクが特に懸念されています。
ミズワタクチビルケイソウの拡大を防ぐにはどうすればいい?

釣り具やウェーダーを必ず消毒する
釣行後は必ず、釣り具・長靴・ウェーダー・タモ網を消毒しましょう。
- 5%の塩水に1分間浸ける
- 60℃以上のお湯に1分間浸ける
- 濃度50%以上のエタノールに1分間浸ける
釣行後のチェックリスト
- 道具は必ず洗浄・消毒する
- 乾燥だけでは不十分
- 道具を釣行ごとに分けて使うのも有効
自治体や研究機関への報告も重要
安曇川以外の河川で「綿のような藻の群体」を見つけた場合は、琵琶湖博物館や水産試験場に報告するよう呼びかけられています。
まとめ:正しい知識と対策で被害を防ごう
ミズワタクチビルケイソウは、外来藻類として生態系や釣り環境に深刻な影響を与える存在です。
琵琶湖流域でも発見されており、拡散防止は喫緊の課題となっています。
- アユや水生昆虫の減少など生態系への影響
- 釣り具に付着する実害
- 人の移動による分布拡大リスク
しかし、塩水・熱湯・アルコールによる簡単な消毒で拡大を防げることが分かっています。
釣り人や川を利用する人の小さな行動が、未来の水辺環境と釣り文化を守ります。

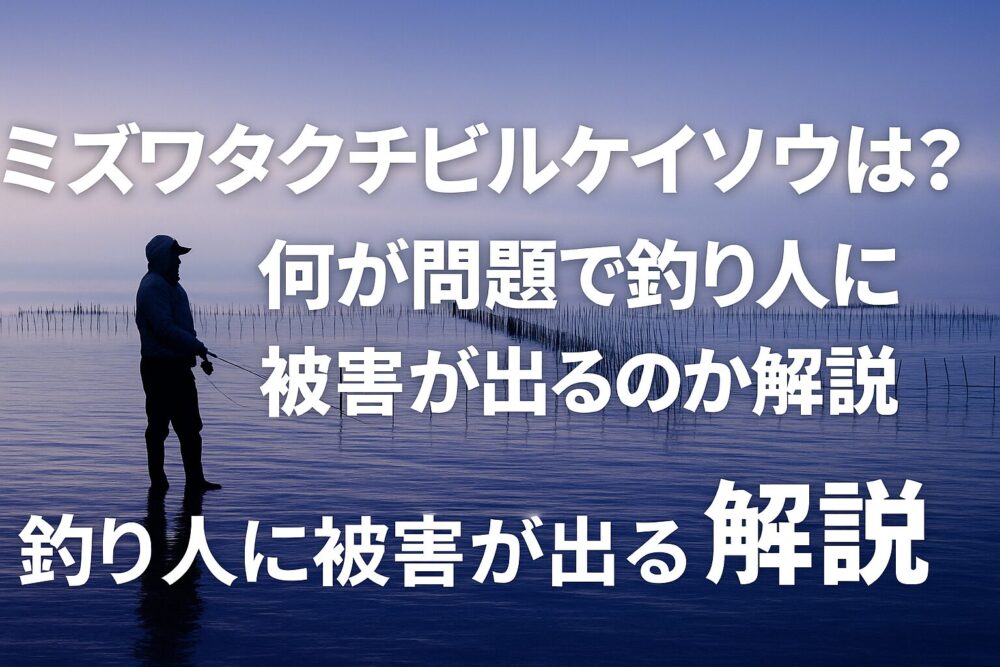

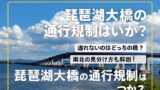


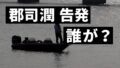

コメント